兵庫県私立小・中・高等学校人権研修会
きょうの午後、兵庫県私立小・中・高等学校人権教育研修会が神戸のラッセホールで行われました。(株)JTBデータサービス総務部定着支援課障害者求人事務局長の笠原桂子氏を講師として「挑戦という名の旅に出よう」という演題での講演会でした。この研修会は、県内の私立学校における人権教育や心の教育等について研修を深めるために毎年行われているものです。本校は県の世話役校になっており、私は県私立学校人権教育協議会会長としてこの研究会に参加しました。
講演の冒頭、「今日のゴールは、この娘たいしたことのない普通の娘だなと思っていただければ」との話から始まりました。友達とうまくいっていなかった公立小学校から、逃避的に国立中学校へと進学、そこで「学力面」での挫折を経験し、卒業後定時制高校へ。定時制高校の中で様々な経験をし大学進学を目指すようになり和光大学へ進学、手話と出会う。「私は頑張って勉強すれば手話で話せるようになるが、聾者は頑張っても聞こえるようにはなれない」と気づき真剣に勉強するように。専門学校を経て手話通訳士となり、現在の仕事につく。仕事をしながらも、さらに深い学びを求め筑波大学社会人大学院へと進み研究者としても活動することに。表情豊かな気持ちのこもった素晴らしい講演でした。
進路や人生の転機、その時々に先生との出会いがあり自分の進むべき道を後押ししてもらったとの話、また、今の自分は教育現場、学校で養われてきたものとの話は学校関係者にとっては身の引き締まる思いでした。講演を聴き終えて、冒頭のゴールの話は、「目立つような子でない、ごく普通の子も様々な悩みや思いを抱え葛藤している生き方をしているということを先生方に知っていただきたい」との指摘だと、私は受け止めました。
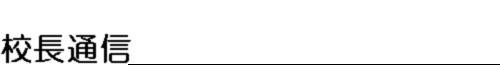


 午前8時30分が過ぎているにも拘わらず、教室に行かず自習コーナーで勉強している生徒が何人もいました。高校3年生は通常の授業とは違いセンター試験と同じ時程で行うセンタープレテストの日だからです。最初の試験が始まるのは9時30分からです。学校に早く来て、テストに備えて準備をしている生徒たちでした。
午前8時30分が過ぎているにも拘わらず、教室に行かず自習コーナーで勉強している生徒が何人もいました。高校3年生は通常の授業とは違いセンター試験と同じ時程で行うセンタープレテストの日だからです。最初の試験が始まるのは9時30分からです。学校に早く来て、テストに備えて準備をしている生徒たちでした。

 中学3年生が沖縄研修旅行から先週の土曜日に帰ってきました。平和学習、環境学習や民泊体験など多くのことを学んできました。この経験や体験を学校生活に活かそうと今週から元気に登校してきています。そこへ、「沖縄からの贈り物」が届きました。それは、環境学習の事前学習としてお招きした沖縄美ら島財団総合研究センターの佐藤圭一先生からでした。「贈り物」は先生が研究されているサメの歯でした。理科の実習助手の方が早速標本を作り、生徒が見られるように生物教室に展示しました。
中学3年生が沖縄研修旅行から先週の土曜日に帰ってきました。平和学習、環境学習や民泊体験など多くのことを学んできました。この経験や体験を学校生活に活かそうと今週から元気に登校してきています。そこへ、「沖縄からの贈り物」が届きました。それは、環境学習の事前学習としてお招きした沖縄美ら島財団総合研究センターの佐藤圭一先生からでした。「贈り物」は先生が研究されているサメの歯でした。理科の実習助手の方が早速標本を作り、生徒が見られるように生物教室に展示しました。 どちらを選ぶか、選択を迫られる機会はいろんな場面で出てきます。目的地へ行くためにどの道を通るかということもあれば、生き方や人生についての道についても同様のことがあります。ただ、決して正解とする道は一本だけでなく、回り道や遠回り、時には道に迷って引き返すことも、でも最終的に同じ目的地に到達するすることは可能です。確信を持って選ぶ道もあれば、ただ道なりに進進んで行く道もあります。振り返ってみて、今在るのは、あの時のあの道を選んだことが大きなポイントになっているという分岐点や転換点のことを「ターニングポイント」という言葉で表したりします。
どちらを選ぶか、選択を迫られる機会はいろんな場面で出てきます。目的地へ行くためにどの道を通るかということもあれば、生き方や人生についての道についても同様のことがあります。ただ、決して正解とする道は一本だけでなく、回り道や遠回り、時には道に迷って引き返すことも、でも最終的に同じ目的地に到達するすることは可能です。確信を持って選ぶ道もあれば、ただ道なりに進進んで行く道もあります。振り返ってみて、今在るのは、あの時のあの道を選んだことが大きなポイントになっているという分岐点や転換点のことを「ターニングポイント」という言葉で表したりします。 本部半島の北西約9km、東西8.4km、南北3km、周囲22.4kmの位置にあり、北海岸は約60mの断崖絶壁、南海岸はほとんど砂浜で、島の中央よりやや東よりに、海抜172mのタッチューと呼ばれる城山(ぐすくやま)がそびえ立っているのが伊江島です。城山に登れば視界は360度、島全体が見渡せる島です。この島は、太平洋戦争の終盤、住民のおよそ半数が命を落とす、過酷な地上戦の舞台となったところでもあります。現在は2,212世帯4,740人(伊江村の資料)が生活し、産業としては花卉(かき)、サトウキビやタバコの生産などの農業、畜産業、漁業、観光業などが行われています。
本部半島の北西約9km、東西8.4km、南北3km、周囲22.4kmの位置にあり、北海岸は約60mの断崖絶壁、南海岸はほとんど砂浜で、島の中央よりやや東よりに、海抜172mのタッチューと呼ばれる城山(ぐすくやま)がそびえ立っているのが伊江島です。城山に登れば視界は360度、島全体が見渡せる島です。この島は、太平洋戦争の終盤、住民のおよそ半数が命を落とす、過酷な地上戦の舞台となったところでもあります。現在は2,212世帯4,740人(伊江村の資料)が生活し、産業としては花卉(かき)、サトウキビやタバコの生産などの農業、畜産業、漁業、観光業などが行われています。 雲雀丘学園中高等学校にコンピュータ(PC)が導入されたのは、昭和61年(1986年)です。CAI教室に24台のPCが設置されました。その後、教室もLAN教室となりPCも増設されていきました。そして、平成11年(1999年)、中高等学校のネットワークが完成し、インターネットにつながるようになりました。この年から中高等学校のホームページ(HP)の歴史が始まりました。当時は、PCこそ生徒用に多くの学校で導入されていましたが、ネットワークを組み教材作成や校務処理に活用したりHPを立ち上げているところは、まだまだ少ない状況でした。また、各家庭のPCがインターネットに接続できるようになるのもこれからといったところでした。
雲雀丘学園中高等学校にコンピュータ(PC)が導入されたのは、昭和61年(1986年)です。CAI教室に24台のPCが設置されました。その後、教室もLAN教室となりPCも増設されていきました。そして、平成11年(1999年)、中高等学校のネットワークが完成し、インターネットにつながるようになりました。この年から中高等学校のホームページ(HP)の歴史が始まりました。当時は、PCこそ生徒用に多くの学校で導入されていましたが、ネットワークを組み教材作成や校務処理に活用したりHPを立ち上げているところは、まだまだ少ない状況でした。また、各家庭のPCがインターネットに接続できるようになるのもこれからといったところでした。
