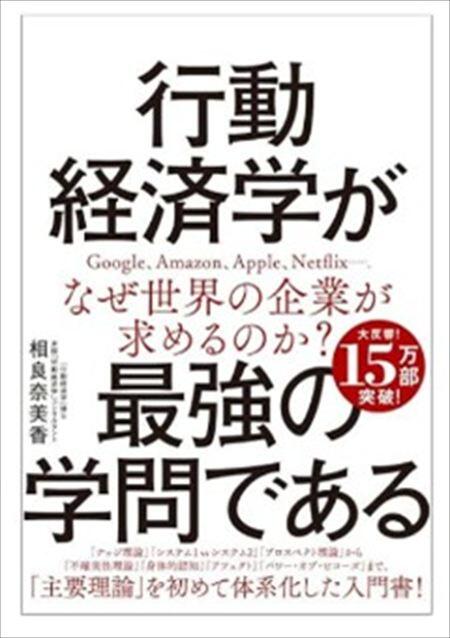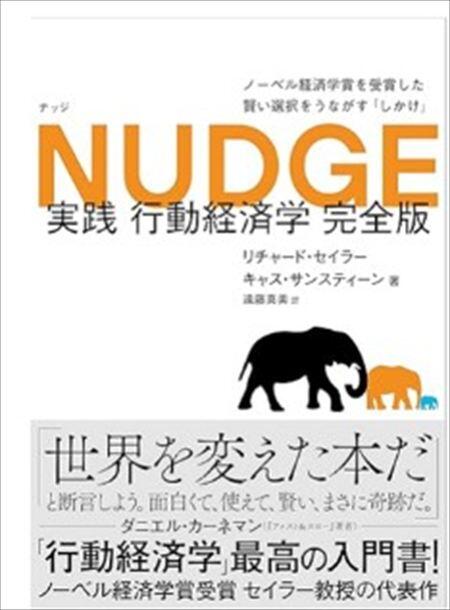探究ゼミ・プロジェクト〔 学内外と連携し、自由に学ぶ 〕
探究ゼミ
探究ゼミ「行動経済学を知ろう」第2回
探究ゼミ「行動経済学を知ろう」、第2回(11/4)のテーマは、2002年に心理学者であるダニエル・カーネマンを中心とした人間行動の特徴(バイアス)の分析を、相良奈美香さんの書いた「行動経済学が最強の学問である」を使って、紐解きました。
本能的な「速い思考」と、進化で手に入れた「遅い思考」。それぞれの思考を適切な場面で使えればよいのですが、高度な情報化社会の登場で、多くの情報と早い判断が必要とする場が増え、「速い思考」を必要とする機会が増えたことにより、我々は、間違った判断をしてしまうことが増えている。それが、「埋没コスト」「概念メタファー」といったバイアスを生むことになったのです。
また、我々は毎日、数多くの意思決定をしていますが、「状況」によっても、意思決定をさせられていることが、行動経済学の理論として発表されています。その代表的な理論である「プライミング効果」「フレーミング効果」「プロスペクト理論」を学びました。
行動経済学は、2017年にノーベル経済学賞を受賞したセイラー教授の唱えた「ナッジ」から、人々に対し強制することなしに、いかに自発的に行動変容を促していくかがテーマになってきます。八王子市での「大腸がん検査キット」事例、「ロンドンのタバコのポイ捨て問題に対するNPOの対策」、「アイスランドでの交通安全対策」を事例として学びました。
次回は、11/11(火)。「ナッジ」の広がりを理解するとともに、大阪大学の松村教授の書かれた「仕掛け学」をご紹介していきます。