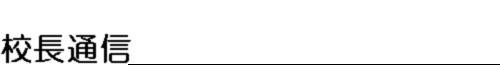沖縄について
11月6日(火)17時頃、生徒達がホテルに無事到着したとの電話連絡が入りました。心配していた天気も少し雨がぱらつく程度とのことで、ほっとしています。
同じ国の西南端に位置するこの沖縄という場所について、我々にはあまり知られていないのではないかと思い、少し調べることにしました。
人口137万人(都道府県別32位)、県面積は2273平方㎞、国土面積の1%にも満たない県であり、島が南北長くに点在し全長約400㎞にも及びます。有人島だけでも49島、他無数の島々からなります。県花はハイビスカスと思われがちですが、実は「でいご」であり、春先に真紅の美しい花を咲かせます。気候は温帯に属し、一部地域は日本唯一の熱帯(亜熱帯性気候)に属します。温暖な気候と小魚や黒砂糖、ゴーヤ、ウコン等の健康食に恵まれ、長寿の人が多いのも特徴です。また、美しいサンゴ礁に囲まれており、年間客数500万人を超える観光客が訪れることでも有名です。沖縄は本土には見られない自然や貴重な動植物も多く残っており、特に本島の北部にある山原(ヤンバル)の森林を中心に、天然記念物なども多く生息しています。また、その気候を生かしてマンゴーやタバコなどの農作物が作られています。古来、サツマイモやサトウキビなど沖縄を通して本土にもたらされたものも多く、変わったところでは格闘技「空手」もそのルーツは沖縄です。
歴史を遡ると、既に8世紀から「阿児奈波(おきなわ)」として知られており、現在の「沖縄」という字を当てたのは江戸時代の学者である新井白石だと言われています。沖縄の人々は土地の訛を交えて「ウチナー」といいますが、14世紀頃から中国(明)と交易、次第に日本・アジア諸国との貿易中継地として栄え、小国ながらも400年以上も独立国家(琉球王国)として独自の文化を形成してきました。日本に完全統合されたのは1870年代ですが、敗戦によって一時日本の統治から離れた後1972年に返還され、日本に最後に加わった都道府県となり今日に至っています。
しかし、長い歴史の中で日中両国による属国支配や連合軍本土上陸の地、戦後アメリカによる軍政支配、そして現在も続いている基地問題等、数多くの悲惨な歴史がある土地であることを忘れてはならないと思います。沖縄の歴史について考え、その文化や伝統を尊重していくことが大切であると思いました。
研修旅行の様子は『中3学年だより』に掲載していますので、参照してください。