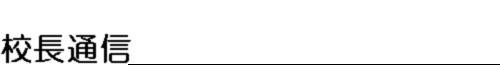OECDの学力調査と日本の国際競争力

日本はこれまで物づくりの分野で世界をリードし、経済大国として発展を遂げてきましたが、これを可能にしてきたのは高度な専門能力や質の高い労働力です。言い換えると教育力が日本を支えてきたのです。
OECD(経済協力開発機構)では、2000年から3年毎に世界の15歳の生徒を対象に学習到達度調査を実施しています。最初に実施された2000年の第1回調査では数学的活用力が1位、科学的活用力が2位、読解力が8位と、世界トップを維持していました。ところが、2003年、2006年の調査では、連続して順位を落とすことになりました。その後、2009年に第4回の学力調査が実施され、日本の高校1年生は前回(第3回)2006年に行なわれた調査に比べて、読解力が15位から8位へ、数学的活用力が10位から9位へ、科学的活用力も6位から5位と、3分野すべての順位を上げるという結果となり、低落傾向に歯止めがかかったようです。
この調査には65か国・地域(OECD加盟国34、非加盟国・地域31)、約47万人の生徒が参加しました。15歳児に関する国際定義に従って、わが国では、調査を実施する学校(学科)を決定し、各学校(学科)から無作為に調査対象生徒を選定し、調査には全国の185校(学科)、約6000人の生徒が参加しました。この結果だけを見ると、日本の生徒の学力は良い方向に向っていると思われがちですが、決して安心できる状況ではありません。
近年、グローバル化の進展に伴い、日本のお家芸であった物づくりにかげりが出てきています。そして、日本の国際競争力は長期低落傾向にあります。今回の学力調査でもトップは上海、次いでシンガポール、香港と国際競争力との高い相関が見られます。日本が技術立国、貿易立国として世界に認められていくためには、更なる学力アップが不可欠であると思います。