防衛大学1次試験合格発表
本日、防衛大学一次試験の合格発表がありました。
本校は、人文社会で54名受験して16名合格、理工は51名受験して31名合格しました。
合格者の合計は47名で、合格率は44.8%でした。合格者数は、過去最高です。
ただ、人文社会系のほうは、厳しい結果となりました。
力があると思われていた生徒でも残念ながら、合格できなかった生徒もいますが、今回の結果を発憤材料として、これからセンター試験、二次試験に向けて、今一度集中力を高め、日々の授業を大切にしながら取り組んで行ってほしいと思います。
この緊張感、真剣味を持ってもらう為に、皆さんに防衛大学の受験を勧めたのですから・・・。
以前にも、防衛大学は合格するだろうという文系の生徒達が不合格になり、本人も先生方もかなりショックを受けましたが、そこから再び目の色を変えて学習に取り組んだ生徒が、念願の第一志望の大阪大学や神戸大学に見事合格しました。
高くジャンプするためには一度、膝を曲げて低い姿勢となってから飛び上がるように、本番でジャンプできるように、これから力を蓄えていきましょう。応援します。
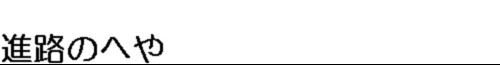
 「看護系大学には、それぞれ特色があって、どんな看護師になりたいかを考えながら選ぶのがよいです。チーム医療に強い大学、地域密着型の大学、国際看護に強い大学など様々です。国公立大学は研究色が強く、県立大学は各県の医療行政を反映した地域密着型という傾向があります。大学を選ぶときは、附属病院と連携した教育プログラムに注目するとよいです」とアドバイスされました。
「看護系大学には、それぞれ特色があって、どんな看護師になりたいかを考えながら選ぶのがよいです。チーム医療に強い大学、地域密着型の大学、国際看護に強い大学など様々です。国公立大学は研究色が強く、県立大学は各県の医療行政を反映した地域密着型という傾向があります。大学を選ぶときは、附属病院と連携した教育プログラムに注目するとよいです」とアドバイスされました。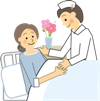 看護師に診断処方を認めるNP(ナースプラクティショナー)は、まだ日本では認められていません。医師法の改正が必要で、まだ見通しは立っていません。しかし、医療がますます高度化していますので、看護師の専門化・多様化は一層進みますので、キャリアのベースとして、4年生の看護系大学への進学を勧めたいです。看護師になるためには、3年生の看護短大や看護専門学校もありますが、将来のキャリア形成を考えますと、不利になる恐れがありますと井上教授は話します。井上教授は「たとえば、専門看護師になるには大学院で学ぶことになりますので、短大生や専門学校生は大学院の入学資格を得るために苦労します。通信教育や放送大学で学位を受ける人もいます、同じ看護師の資格だから、教育期間が1年短い短期大学や専門学校のほうが有利だろうという考えは、結果的には回り道になる場合があります。」
看護師に診断処方を認めるNP(ナースプラクティショナー)は、まだ日本では認められていません。医師法の改正が必要で、まだ見通しは立っていません。しかし、医療がますます高度化していますので、看護師の専門化・多様化は一層進みますので、キャリアのベースとして、4年生の看護系大学への進学を勧めたいです。看護師になるためには、3年生の看護短大や看護専門学校もありますが、将来のキャリア形成を考えますと、不利になる恐れがありますと井上教授は話します。井上教授は「たとえば、専門看護師になるには大学院で学ぶことになりますので、短大生や専門学校生は大学院の入学資格を得るために苦労します。通信教育や放送大学で学位を受ける人もいます、同じ看護師の資格だから、教育期間が1年短い短期大学や専門学校のほうが有利だろうという考えは、結果的には回り道になる場合があります。」 看護師は、看護管理者として病院の副医長になるほか、いろいろなところで活躍しています。身近なところで言うと、園児の健康管理を行う保育園の看護師、産業医とチームを組んで社員の健康管理を行う企業の保健師、厚生労働省や文部科学省、各都道府県などの職員として、医療や看護の政策立案に携わる仕事もあります。最近では、治験コーディネーターなど、看護師のスキルを生かす新たな分野もありますし、JICAで活躍する看護師もいます。
看護師は、看護管理者として病院の副医長になるほか、いろいろなところで活躍しています。身近なところで言うと、園児の健康管理を行う保育園の看護師、産業医とチームを組んで社員の健康管理を行う企業の保健師、厚生労働省や文部科学省、各都道府県などの職員として、医療や看護の政策立案に携わる仕事もあります。最近では、治験コーディネーターなど、看護師のスキルを生かす新たな分野もありますし、JICAで活躍する看護師もいます。 看護師の就職先として増えているのが、介護老人保健施設や訪問看護ステーション、社会福祉施設などです。これまでの訪問看護ステーションで働く場合、新卒でまず病院看護師を経験した後、転職するのが一般的でしたが、訪問看護の需要が高まり、訪問看護ステーションが新人看護師を受け入れ、病院と連携した研修制度の導入が進んでいます。訪問看護の研修も充実してきています。
看護師の就職先として増えているのが、介護老人保健施設や訪問看護ステーション、社会福祉施設などです。これまでの訪問看護ステーションで働く場合、新卒でまず病院看護師を経験した後、転職するのが一般的でしたが、訪問看護の需要が高まり、訪問看護ステーションが新人看護師を受け入れ、病院と連携した研修制度の導入が進んでいます。訪問看護の研修も充実してきています。 キャリアアップの選択肢の一つとして、「専門看護師」と「認定看護師」の資格取得を目指す看護師が増えています。専門看護師は大学院で専門の教育課程を修了し、日本看護協会専門看護師認定審査の合格する必要があります。認定看護師は6か月、615時間以上の研修を経て、日本看護協会認定看護師認定審査を受けます。
キャリアアップの選択肢の一つとして、「専門看護師」と「認定看護師」の資格取得を目指す看護師が増えています。専門看護師は大学院で専門の教育課程を修了し、日本看護協会専門看護師認定審査の合格する必要があります。認定看護師は6か月、615時間以上の研修を経て、日本看護協会認定看護師認定審査を受けます。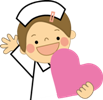 「看護師のキャリアパスについて」、日本看護協会の川本利恵子常任理事と東京医科歯科大学の井上智子教授に取材した記事(学研情報誌)から抜粋してご紹介します。
「看護師のキャリアパスについて」、日本看護協会の川本利恵子常任理事と東京医科歯科大学の井上智子教授に取材した記事(学研情報誌)から抜粋してご紹介します。 <MSF(国境なき医師団)を目指すにはどんな知識や能力が必要ですか?>
<MSF(国境なき医師団)を目指すにはどんな知識や能力が必要ですか?> 黒﨑伸子さんは、長崎大学医学部を卒業された外科医で、現在、「国境なき医師団」の日本会長です。学研・進学情報誌に、黒﨑さんのインタビュー記事が載っていて、印象深かったところをご紹介します。医師を目指す皆さんは、黒﨑さんの言葉を少し心にとどめておいてほしいと思います。
黒﨑伸子さんは、長崎大学医学部を卒業された外科医で、現在、「国境なき医師団」の日本会長です。学研・進学情報誌に、黒﨑さんのインタビュー記事が載っていて、印象深かったところをご紹介します。医師を目指す皆さんは、黒﨑さんの言葉を少し心にとどめておいてほしいと思います。


 普段見ることのできないような機器や部屋などを説明も交えながら見せていただけたので、将来のためになる経験ができてよかったです。初めて見る機器や、ドラマの中で見たことのある機器を間近で見ると、すごく気分が高揚しました。また、患者さんの立場にたって考えることの大切さを診療を通して実感することができてよかったと思います。患者さんの意志と医師の選択の違いをどう埋めていくかを学ぶことができました。今回の体験でモチベーションをあげることができたので、これから先も頑張っていきたいと思います。(実施病院 尼崎医療生協病院 / 実施日 2014年8月5日)
普段見ることのできないような機器や部屋などを説明も交えながら見せていただけたので、将来のためになる経験ができてよかったです。初めて見る機器や、ドラマの中で見たことのある機器を間近で見ると、すごく気分が高揚しました。また、患者さんの立場にたって考えることの大切さを診療を通して実感することができてよかったと思います。患者さんの意志と医師の選択の違いをどう埋めていくかを学ぶことができました。今回の体験でモチベーションをあげることができたので、これから先も頑張っていきたいと思います。(実施病院 尼崎医療生協病院 / 実施日 2014年8月5日) 今回私は進路を決定する参考になればと思い、この体験に参加させていただきました。しかし、冒頭に見せていただいた「笑って死ねる病院」のドキュメンタリーなどから、進路という狭い考えよりも今の病院の現状や医師の思いなども感じることができ、有意義な時間だったと思います。また、体験・院内見学では、作業療法士や理学療法士、放射線技師の方たちが、医師とうまく連携して、かつ自らの仕事にプライドを持っている姿を見ることができて、やはり医療の現場はかっこいいものだと思いました。
今回私は進路を決定する参考になればと思い、この体験に参加させていただきました。しかし、冒頭に見せていただいた「笑って死ねる病院」のドキュメンタリーなどから、進路という狭い考えよりも今の病院の現状や医師の思いなども感じることができ、有意義な時間だったと思います。また、体験・院内見学では、作業療法士や理学療法士、放射線技師の方たちが、医師とうまく連携して、かつ自らの仕事にプライドを持っている姿を見ることができて、やはり医療の現場はかっこいいものだと思いました。 私は春もお邪魔しましたが、今回は念願の外科ということもあって、大変楽しみにして来ました。 前回(春)は、地域医療の意義などについて考える機会になりましたが、今回は広い視野で「外科」の存在について考える機会になりました。ずっと外科は手先が器用でないといけないからうまくできなければあきらめなければいけないと思っていたので、練習すればするだけうまくなるとお聞きして安心しましたし、今から勉強においても根気強くがんばろうと思いました。縫合体験はすごくおもしろかったです。初めてやりましたが思っていたより難しくて、両手が思うように動いてくれませんでした。縫合は外科の基本ですし、機会(手術ロボット)を扱うにもできなければいけないことだと思うので、外科医になれたら一生懸命練習しようと思いました。
私は春もお邪魔しましたが、今回は念願の外科ということもあって、大変楽しみにして来ました。 前回(春)は、地域医療の意義などについて考える機会になりましたが、今回は広い視野で「外科」の存在について考える機会になりました。ずっと外科は手先が器用でないといけないからうまくできなければあきらめなければいけないと思っていたので、練習すればするだけうまくなるとお聞きして安心しましたし、今から勉強においても根気強くがんばろうと思いました。縫合体験はすごくおもしろかったです。初めてやりましたが思っていたより難しくて、両手が思うように動いてくれませんでした。縫合は外科の基本ですし、機会(手術ロボット)を扱うにもできなければいけないことだと思うので、外科医になれたら一生懸命練習しようと思いました。 少しずつは大学卒業生の就職難が改善されてきているようですが、日本に多くの留学生が入ってきている今、日本の学生は海外の学生と就職でも競争しなければなりません。
少しずつは大学卒業生の就職難が改善されてきているようですが、日本に多くの留学生が入ってきている今、日本の学生は海外の学生と就職でも競争しなければなりません。 国公立大学で就職支援ネットワークができはじめています。現在は11大学の参加でスタートし始めていますので、その情報をお知らせいたします。本情報は、主に、学研の進学情報誌から得ました。
国公立大学で就職支援ネットワークができはじめています。現在は11大学の参加でスタートし始めていますので、その情報をお知らせいたします。本情報は、主に、学研の進学情報誌から得ました。


