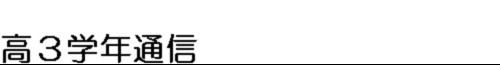春の嵐と高校校舎の涙!?
昨日は午後から雨が降り始め、夜には強い風を伴って、時ならぬ春の嵐となりました。黄砂も到来し、春が一歩ずつ着実に近付いていることが感じられます。しかし、大変なこともありました。1年B組の教室が雨漏りで水浸しに!担任の松石先生曰く、「あと一週間で取り壊される高校校舎の最後の涙かなあ…」。でも、後始末は大変。何とか一時間目の授業を迎えることができました。季節の移ろいを感じながら、人と人との繋がりを大切にし、日々を過ごすという当たり前のことが一番だということを今更ながら感じます。では、経済の話の最終回を…。
21世紀初頭、百年ぶりといわれる世界的大不況が吹き荒れる現在に立ってポランニーが指摘した市場主義経済の問題点を顧みるとき、その指摘がいかに的確であったかを、改めて確認することができる。彼の指摘は、全くの的外れであり、いにしえに対する無批判な懐古主義に過ぎないと切り捨てる経済学者もいる。しかし、現在世界中の全ての国で起こっているといってもよい失業者の増大は、まさに労働の商品化の結果に他ならない。では、なぜ我々の経済は失敗したのか、どうすればその失敗を取り戻すことができるのであろうか。
ポランニーは、経済には二つの意味があることを示したが、さらに市場経済化する前の社会に対する研究から、「市場化により効率よく機能する経済領域」と「市場化そぐわない経済領域」が存在することを明確にした。その両者を混同せず、社会の中で「経済とは違う原理=政治や地域社会」がその境界を明確に見極め、後者を「市場化の嵐」から守ることこそが重要である。古代や無文字社会においては、そうしたことが無意識に行われていたことをポランニーはその研究によって描き出したのである。それがまさに「経済を社会に埋め込む」ということに他ならないといえよう。
少なくとも第二次世界大戦後に、その反省の下で成立したブレトン・ウッズ体制の理想を受けて、国家は国民の権利と財産を守り、教育や福祉を充実させた時期があった。しかし、ここ20年ほどの間に、アメリカの一国偽善主義の影響下で、日本のみならず、全世界で、教育や文化・医療・福祉といった、本来は市場経済原理とは無関係であるべきものが、「市場化」・「商品化」の危機にさらされ、崩壊の危機に瀕している。
アダム・スミスは、『国富論』の中で市場主義経済は「見えざる手」によって、調整されると説いたが、それは「自由放任」を許容したということではない。一方で、スミスは『道徳感情論』の中で、人間には賢明な選択と欲を求めようとする利的な意識が同居し、後者が経済の発展を促す原動力となっているが、経済が調整を行う根底には、人間としての「同感」があることを述べている。つまり、スミスは野放図な経済の暴走は、まさに人間同士の繋がりの意識によって止められるということを指摘しているのだ。そして、これは、ポランニーが指摘した「経済が社会に埋め込まれている」状態と同じことを示していると言えないだろうか。
日本の一流企業と呼ばれていた大企業にも、減益・減収の嵐が吹き荒れ、非正規労働者のみならず、正社員の解雇までが報道されている。なぜ、このような事態を迎えたのであろうか。ここ20年ほどの間に、日本の企業も、やれグローバリズムだ、イノベーションだと、アメリカ発のハイリスク、ハイリターンのマネーゲームに巻き込まれていった。その結果、一流であったはずの日本の大企業が、その創業者達が掲げた理念を忘れ、業績は一流でも、行動は三流になってしまったというのは、言い過ぎであろうか。日本には、江戸時代以降、石田梅岩の心学、二宮尊徳の報徳仕法、内村鑑三の「経済道徳論」など、優れた経済思想が存在している。今一度自分の足元を見直して、改革は何でも正しいという一方向的な思考を改め、不易と流行を見極めることをゆっくりと考えてみてはどうだろうか。
「経済」が「社会」を支配する時代は、終わりを告げた。「人間」が「経済」を取り戻すときが来たのだ。これからも、「効率」や「成果主義」がすべて正しいといった単細胞な論理に流されず、雲雀丘学園が60年にわたって営々と育んできた、良い意味で余裕をもった豊かな教育を続けていくことこそが、大切だといえるだろう。
【連絡】月曜日は、英単語大テストです。合格点目指して頑張りましょう。高一で身につけた単語の基礎力が、受験にも大きな役割を果たします。