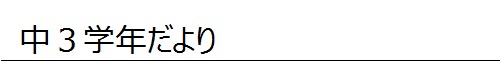七草がゆ
今日は「人日(じんじつ)の節句」です。節句は通常、3月3日や7月7日など数字の重なる日となりますが、1月のみ7日となっています。中国の風習にならってのことらしいですが、それだけ1月1日が特別であるともいえます。人日とは中国では「人を大切にする」という意味があるとか。まさに本校の親孝行に合った節句でしょう。
さて、この日は「七草の節句」ともいいます。早春にいち早く芽吹くことから、邪気を払う意のある七草を無病息災を祈って食べてきました。この行事が平安時代より続いてきたのは、効能のある七草を胃腸に負担がかからないお粥で食べるのは、正月疲れが出はじめた胃腸の回復という意味でも理にかなっていたのでしょう。
最近はスーパーで写真のようなセットが並んでいます。明治時代、旧暦から新暦に変更するにあたり、季節感はひと月ほどずれてしまいました。今のようなハウス栽培などのない時代、新暦へと変わった頃の人はどのように七草を集めていたのでしょうか。以下、春の七草とその効能です。
・せり =整腸作用、血圧降下作用
・なずな =解毒作用、止血作用
・ごぎょう =咳やのどの痛み
・はこべら =腹痛薬や胃炎、歯槽膿漏
・ほとけのざ =食欲増進、歯痛
・すずな =消化促進
・すずしろ =風邪予防、美肌効果