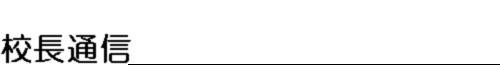〝つ〟のつく教育
教育関係の仕事に従事するようになってから5年が経過しましたが、日々子ども達と接していて潜在能力に大きな差があるようには思えません。学力の差が生じるのは、学習をはじめとする生活習慣や集中力ややる気が影響しているように思います。先生方もどうすれば子ども達の人間力や学力を高めることができるのかということを常に考えながら指導を行なっていますが、すべてが思い通りにいくとは限りません。私も就任以来、どのようにして生徒を育成していくかということが頭の中から離れません。そのため、教育関係者だけでなく、小児科医や大脳生理を研究している方々ともよく懇談するようにしていますが、しばしば参考になる意見をいただくこともあります。その一例が〝つ〟のつく教育という内容です。解り易くいえば、年齢に〝つ〟のつく年、つまり「1歳=一つ」「2歳=二つ」三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、「9歳=九つ」の教育が非常に大切であるということです。以前、PTAの役員の方からも「私の祖父は小学校の校長をしていたが、〝4年生までの教育が大切である〟と常々語っていた」という話を披露していただきましたが、これには明確な根拠があるようです。
小学校に入学する(6歳)までの子どもの態度は、まねる→欲しがる→やりたがる→自分でやるということであり、この時期には豊かな愛情を与えるための母子のふれあいが不可欠です。そして、小学校に入学してからの2年間は、学習に親しみ楽しむということが基本になります。そのためには、習慣づけ、やる気、集中力、考える力、親子の対話が必要だということです。
この8歳までが幼児教育という位置づけになっており、9歳からは自発的な学習に入ることになります。つまり、この歳までにしっかりとした学習習慣をつけておくことが、将来の学力の伸びに繋がっていくのです。基礎が何よりも大切であるという認識に立って、子ども達の育成に取り組んでいかなければならないと思っています。