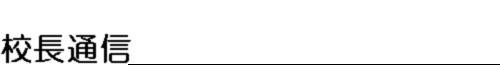ひな祭り

「あかりをつけましょ ぼんぼりに お花をあげましょ 桃の花・・・」。きょう3月3日はひな祭りです。上の写真は、職員室に飾ってある手作りのおひな様です。本校に通う生徒のおばあさまから頂いたものです。
ひな祭りは、中国から伝わってきた五節句、人日(じんじつ・1月7日)、上巳(じょうし・3月3日)、端午(たんご・5月5日)、七夕(たなばた・7月7日)、重陽(ちょうよう・9月9日)のなかの上巳の節句、旧暦の3月3日に行われており、桃の花が開く頃で「桃の節句」とも言われています。春先に農作業をはじめるにあたって、物忌み、禊などを行い穢れを払う行事とされていました。人形はもともとこの汚れをうつして川などに流す「形代」として使用されていたようです。ですから、古くは特に女の子の祭りというわけではなく、男女が共に参加していたようです。今では、ひな人形に桃の花を飾って、ちらし寿司に蛤のお吸い物などを食べ、娘の厄よけと健やかな成長を願う、親が子を思う気持ちを伝える大切な行事になっているように思います。
子を思う親の気持ちを伝えることは、時として難しい時があります。特に、思春期、反抗期と言われるときはそうです。文字通り、反抗期、何も聞いてくれないときがあります。しかし、これは気持ちが伝わっていないのではないのではありません。伝わっているのですが、その気持ちを素直に受け入れてくれない。子どもなりの考え、意見を持とうとしての「反発・反抗」です。あふれる愛情を受けて育った子どもは、あふれる愛情で人に接する子どもに成長すると信じています。おばあさまに頂いたひな人形、職員室から全校生徒に「親が子を思う気持ちを」あふれるほど伝えてくれています。