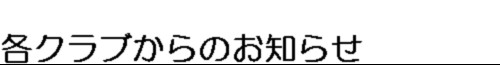環境大使 椎茸栽培体験パート2
2月5日(日)、環境大使11名と担当教員とで篠山市の辻生産組合、青野会長の山へ行ってきました。青野様には、前回の黒豆栽培の際にも畑をお借りして本校の教育活動にご助力をいただいています。今回は、椎茸栽培体験の第2弾です。椎茸栽培の行程は、おおまかに原木採集→菌の植え付け→椎茸採集となります。、前回は森に椎茸の原木を探しに入り、のこぎりで切って、菌の植え付けをする準備までの行程を体験しましたが、いよいよ椎茸の菌を原木に植え付けることとなります。
大使たちが集合した場所にはたくさんの栗の木が生えていました。この場所は以前は田んぼでしたが、今は栗の木を植えているそうです。栗の木は水がある場所には育たないため、植え付けの際にはユンボで根を切る作業をするそうです。水のいらない木もあるんだ・・という大使のつぶやきの中、確かに、周りを見ると、水田の真ん中あたりに植えられている栗の木の育ちは良くなく、適所でこれだけの違いがでるのだなと実感しました。栗の木は3年で根が枯れるため、青野さんが力を入れて押すとぐらりとゆれます。「やりたい!」という大使の声に、木を抜く作業も体験させていただきました。


いっせーのーで!抜けた! 火を熾していただいていました。暖かい^^
この栗の木、触ってみると大変固い!!!建材に利用すると120年以上ともいわれる耐久性があると教えていただきました。鉄筋ではその耐久性は50年が限界といいますから、その素材の強固さが伺えます。しかし、今はその建材はあまり使われなくなっているそうです。木材の輸入が解禁になった時期から、大量のラワン材が国内に入ることになったからだそうです。このラワン材は南方で育つため、四季のある日本の木材のように年輪が過密でなく、耐久性がない材木でもあります。しかし、膨らし粉を入れたように、すぐに大きく育つため、安く、大量に納品することが出来ます。結果、日本の材木が売れにくくなり、その値段と折り合うために一石の値段が( 材木の単位:で1石は0.278立方メートル)、の10分の1程度という安さに下がってしまったのだそうです。日本の林業は50~60年(!)もの時間と労力を費やす大変な仕事です。その材木の価値に見合った収入を得ることができなくなり、林業から離れざるを得ない状況が生じてしまったのです。節のない真っ直ぐないい材木を作るためには、枝打ち、下草狩りが必要で、その作業が自然と森林保護にもつながっていました。木の世話をしなくなったことで、森が荒れることになったのです。また、、松は山の7合目より上に生える木なので、風が山の上まで届かなくなると生えにくくなります。このように、輸入木材の流入は、篠山の松茸など、特産品をも希少なものに変えてしまった、というお話でした。最後に、「桃栗3年、柿8年といいます。僕は今年77歳ですが、今柿を植えたら85歳。まだまだ植えていこうと思っているよ」とおっしゃる青野さんのお話に、元気と、若さと、たくさんの笑顔もいただきました。


栗の木の下で・・ 下草刈りの様子
ユーモアも交えながらたくさんのお話をしていただき、大使たちも色々と感じるものがあったことと思います。特にTPPについては、ニュース報道などで身近な話題ではあったものの、それを環境と結びつけて考えることは少なかった大使たちですが、青野さんのお話を聞いて、経済がすなわち環境であるということを、実感として感じたようです。日本の米の関税は?と聞かれて即答できない大使たちに「778%」という青野さんの答え。それがなくなると、半額ほどの安い米が国内に流れ込んでくると言います。林業と同じようなことが今度は田んぼで起こるのでは・・。その利潤と、一方で失うものとの狭間でまた一つ熟考する機会を得たようです。いつも青野さんには、体験に絡めながら様々な深慮のあるお話をいただいています。今回も、実際に木や森、田んぼを感じながら聞いたお話は、大使たちに日本の農業の保全とそれにつながる環境について実感として伝わったことと思います。


ドリルの使い方を聞いています このようにして・・・


椎茸の菌のついたタネを・・ 協力して埋め込んでいきます
その後、枝打ちを体験し、道具の安全な使い方などを教えていただいて、いよいよ椎茸の菌付けです。
前回採取した原木に、ドリルでチドリ型に穴をあけ、菌のついた種を埋め込んでトンカチで叩いていきます。重たい原木を支えてまわしながら均等に菌付けをしていきました。できたものは運んで井形に積んでシートをかぶせ、作業は無事終了。垂直にドリルを入れるのが難しく、苦労しましたが、協力して行うことが出来たようです。その後、いつものように森の下草狩りの作業を行い、昼食をとりました。休憩時には青野さんがお芋とあたたかいお茶を用意して下さり、たき火を囲んで焼きたてのアツアツの焼き芋をいただきました。たき火でお芋を焼いたのは初めて!という大使も多く、黄色のきれいなお芋に歓声があがっていました。ごちそうさまでした。
ご助力いただきました青野様、ありがとうございました。
篠山の畑での作業は、今年度はこれで最後になります。次年度環境大使の募集は2下旬に予定しています。興味のある生徒の皆さんは奮って参加してくださいね!