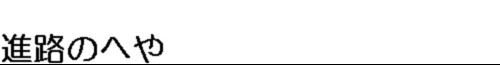AO入試
大学の入試方式で近年わが国の入試制度に強いインパクトを与えたのはAO入試でしょう。AO入試という耳慣れない用語を聞き始めたのは、1990年(平成2年)からです。『OA入試』のうち、『AO』というのは ‘Admissions Office’ のことで、これを始めて聞いたときは、アメリカ流の入試方式の一つのことなんだろうと簡単に受け取っていました。しかし、とにかくそれはとても新しい方式らしいという感じはしま
た。
それ以前の推薦入試に、例えば亜細亜大学が行った一芸入試という風変わりな入試がありました。魚を三枚におろす特技で合格した受験生がいたらしいなんてことが、真偽のほどはともかく、噂になったこともありました。現に、担任をしていた我がクラスからこの亜細亜大学の一芸入試で入学を果たした生徒がいました。(何の特技で合格したのか、なにしろ1990年以前のことで、残念ながら忘れてしまいました。)
しかし、この『OA入試』というのはそれまでのその種類の入試制度と異なり、画期的に新しいらしいということが段々分かってきました。『AO』というのは ‘Admissions Office’ のことだから、『入学許可事務局』とでもいった意味で、この事務局が扱う推薦入試の一種だろうというふうに考えていましたが、ここが一番違う点で、AO入試というのは推薦入試ではない。つまり、推薦は不要だということです。さらに、入学『試験』でもないらしいのです。
無知をさらけ出すようですが、戦後の日本の教育制度はアメリカのそれをを模倣しているのだから、迂闊にも、アメリカにも日本のように入学試験があって、大学の教員が入試問題をつくるものだと漠然と考えていました。ところが、アメリカでは入学生の選抜に当たっては、教員はタッチしないものらしい。この事実にはまったく驚きました。合衆国には入学試験はなくその代わりに、ETS(Educational Testing Service)というテスト業者(因みにこの業者はおなじみTOEIC とかTOEFLなどの英語検定試験も作っています)が年数回全世界で行うSAT(Scholastic Assessment Test)とAssessment Program が行うACT(American College Test)というテスト結果を入学基準にするらしい。SATが共通テストという意味では日本の大学入試センターの行うセンター試験に似てはいますが、日本の場合、これはほんの予備試験のようなもので、その後それぞれ個別の大学の教授たちが腕によりをかけた二次試験が待ち受けているわけですから用途はまるで異なります。もちろん、選抜に当たっては書類選考が基本となるようです。
AO入試を日本で華々しく導入したのは慶応大学のSFC(湘南藤沢キャンパス)の総合政策学部、環境情報学部でした。前述のように1990年のことです。「筆記試験によらず書類審査と面接によって多面的、総合的に評価」されるもので、従来の筆記試験による入試と激しく対立するものでしたから話題を呼びました。尤も、アメリカのような事務局はないので、事務員と教員がほぼ総動員で、膨大な経費と時間をかけて実施されたようですが結果は大成功で、大学側の思惑通り一般的な入試では得られないような優秀で、個性的な学生を確保できたようです。
事実、多くの学生のベンチャー起業家や、Webコンテンツ産業の創業者が輩出し、起業家を育てたり、メディア産業にも優秀な人材を多数送り出したりして華々しい出発をして話題を呼びました。
文責 山本正彦