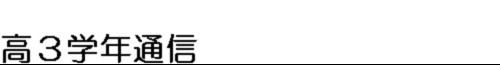模試を読む

国語の監督中,試験問題をめくっていたら,「下流志向──学ばない子どもたち、働かない若者たち(内田樹 著)」の引用文が載っていた。
要約(+意訳)すると,
「今の子供たちは,幼いときから,消費主体として行動することを憶えた。お金さえあれば,小さい子供であろうが老人であろうが,丁寧に対応され,コンビニで好きな商品と交換できる。お金は持つ人の身分を問わない(貨幣の透明性)。この経験はその子の中に大きな影響を残し,重大な価値観を生む。あらゆることを消費的側面から捉え,得か損か,等価交換「取引」で考える癖がつくようになる。
教室における貨幣は「不快」である。その代償を払って受ける教育サービスが等価交換かどうか,彼等はそれを「この勉強は何の役に立つのですか?」と表現する。そして,できるだけ少ない消費で(=サボって),大きな買い物(=成績や大学)をしようとする。それが,同世代同士で比較して,スマートで,クールでかっこいい生き方だと信じて疑わない。
勉強しないのは,やる気がないのではなく,「どうせやったって・・・・」ただ「不快」だけであり,得るものがない-消費行動から来るものだ。そして,下位であっても不利益を被ることがなく,「損」にはならないからだ。」
確かに,何に対しても上昇志向のない若者が増えた。すぐ値踏みして,「つまらん」という。○か×かしか答えがない。しかも,ほとんど×。駆け引きが下手だと思う。
ところで,生徒は設問に答えるのに必死だったが,私の方は面白いなぁと感心していた。せっかくなら,指示語の内容とか漢字の書き取りとかだけでなく,反論を書かせる問題があったら面白いだろうなぁと思ったのは,試験を受けていない身のせいか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【配布物】文理選択に役立つモノ
1.進学講演会資料
2.大学案内請求カタログ
3.代ゼミデータブック(部数限定希望者のみ)