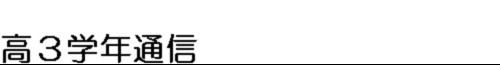書いたままになっていた学年通信2
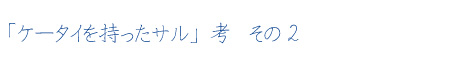
著者は,最近の若者に特徴的な行動パターンは,「家のなか主義」ともよぶべきライフスタイルに集約されるとまとめている。靴のかかとを踏む,ネクタイやリボンをルーズに結ぶ,階段や電車,あげくはトイレの前でへたり込む,固定した交友関係しか作らない,等々は,緊張を強いられる外の関係を嫌い,家のなかと同じ態度を貫こうとする,開き直った姿勢の現れなのだと。
こうしたケータイ世代のサル化現象は,密着した母子関係に原因があると言い放つ。いわば,「子ども中心主義」は,成熟した大人になることを拒否する子どもの態度を擁護し,子どもの自立を阻害しているのだと強調する。そして,益々,居心地が良い「家のなか主義」を助長させていると。なるほどな,と思う。
くわえて,この世代の子どもは「群れ」たがる。同じものを着,同じ格好をし,仲間だけに通じる言葉・話題で閉じた集団をつくろうとする。群れることはそれ自体悪いことではない。自立する前の準備段階であり,昔の高校生も群れていた。しかし,そのベクトルは社会に向いていた。
ところが今は違う。若年購買層として保護されているためである。ケータイが与えられ,ゲームが認められ,この世代は大きな市場として魅力を持っているからだ。そこに「群れ」の習性が加わり,ルーズ・ケータイ・メールは格好の道具となったのである。
群れの習性-一旦受け入れられると,それは止めどなく続く。際限なく改良が加えられ,どんどんエスカレートしていく。茶髪,靴べた,ズボン下げ,ルーズタイ,メール,ブログ,ブロフ・・・・。
一体,この群れはどこへ行こうとしているのだろうか。ただただサル化するだけなんだろうか。考えてみれば,群れが創り出すエネルギーは,社会に影響を及ぼすほどに大きい。このまま内部消費するのはいかにももったいない気がする。むしろ,この群れのエネルギーを外に向け,様々な問題を抱え悩む世界に向ける方法はないのだろうか。学校の役割は大きいと思う。