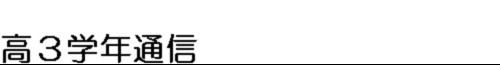ちょっと難しい経済の話 その3
今日は「建国記念の日」という祝日ですが、本校では昨日の高校入試A日程の入試会議とその結果の発送作業がありました。また、経済の話の続きをご覧下さい。
さらに、1980年代末のソ連崩壊により東西冷戦が終焉すると、世界はアメリカ合衆国一国のみが超大国として君臨する新しい段階を迎えた。それは、インターネットに代表される情報化と新自由主義、そしてグローバリゼーションという名の“アメリカ化”に他ならなかった。世界は一端崩壊した自由主義のイデオロギーを復活させかに見えたが、それは、同じ顔つきをした全くの別物であった。
新自由主義は、経済に対する国家の一定の規制を認めたケインズ主義を駆逐し、国家の政策においては「個人の自由を尊重する」=「個人の責任を重視する」という視点から、教育や福祉の予算を削減する一方で、経済の発展のみが国家の発展であるかのように、各国が規制緩和を掲げて競い合って市場を開放、株式市場は投機マネーが大量に流入し、かつての「自由放任」よりもさらに悪化した市場経済が現出した。ここにおいて、国際経済における「ブレトン・ウッズ体制」の理想は、放棄されたといっても過言ではない。さらに、事態を悪化させたのは、この間に急速に進展した情報化のもとで一気に加速したグローバリゼーションにより、一国の経済は、国際経済の変動の波に否応なく翻弄されることとなった。多国籍企業が跳梁跋扈し、一部の経済学者によって“グローバル・カジノ”と呼ばれる世界的な投機ゲームが象徴するように、「悪魔の碾き臼」は国や地域という枠組みを超えて巨大化してしまった。グローバルカジノ化の大きな原因に、金融工学とゲーム理論の応用がある。サブプライムローンの破綻もまさにその悪しき賜物である。金融工学とは、様々な債権などを組み合わせて、それに色々な要因に関わる係数を掛けて、よりリスクが少なくなるように分散して「金融商品」を創り出して投資するという、いわば“情報化社会の鬼子”であった。ファンドと呼ばれるいわば“賭け事師”に世界中の「形式的経済」によって生み出されたあぶく銭が集まり、世界中の人々の生活の根底を覆すかも知れない、危険なカジノを楽しんでいたのである。しかし、人間の営む現実世界は、どれほど性能の良いコンピューターでも解析ができないほど複雑で、偶然に満ちている。サブプライムローンの破綻によって、世界経済が総崩れになったことは図らずもそのことを証明することとなったのである。金融工学やゲーム理論という化け物が、世界中を破壊し尽くしていたときに、我々はやっとその現実に気付いたのだが、それらを制御できなかった政治、特にアメリカの責任はあまりにも重い。
このグローバル・カジノ現象は、「形式的経済」=「社会から断絶した経済」の典型例であるといえよう。今、野放図なグローバル・カジノの崩壊によってアメリカの経済はあっけなく破綻し、それが世界中の「実体的経済」を容赦なく蹂躙している。BRICsなどの新興国の成長の下で我が世の春を謳歌していた世界は、わずか半年の間に奈落の底に突き落とされてしまった。