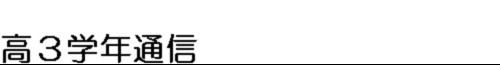ちょっと難しい経済の話 その2
今日は、高校入試A日程でした。現在午後10時前ですが、まだ作業は続いています。
さて、昨日の経済の話も続いていきます。
ポランニーは第二次世界大戦後、古代社会や無文字文化社会の経済を研究対象とし、そこに人間の社会と経済の正しい姿を見出そうとした。古代バビロニアやアフリカのダホメ王国などの分析を通じて、本来人間社会に普遍的に存在していた「非市場経済」が、社会に埋め込まれた仕組みとしてどのように経済活動を営んでいたかを彼は描き出している。
彼は経済的(economic)という言葉には二つの意味があるという。一つは人間の手段と選択をめぐる合理性に関連する形式的意味、つまり単に必要なものを理由の如何を問わず、相手が誰であろうと金銭によって手に入れるという、市場経済における「消費」という行為そのものである。そしてもう一つは、人間が生を営む限り必要となる物質の代謝に関連する実体的・実在的意味である。形式的意味は市場経済のみに存在する。しかし、人間の経済における本質的・普遍的なものは、実体的意味である。この二つの意味を区別せず用いていることに、市場社会の矛盾が解決されない一因があるともいえる。
ポランニーの一生をかけた研究課題は、市場社会の出現によって社会から突出してしまった「経済をいかにして社会に再び埋め戻すか」ということだった。彼の遺稿集の題名は、『The Livelihood of Man』である。「Livelihood」とは「日々の暮らし」・「生活」を意味する卑近的ともいえる言葉であり、「市場社会ではなく、人間の生の営みにこそ経済の本質がある」という、彼のたどり着いた思いをこの題名は示しているのだとも考えることができる。
彼の死後、20世紀後半の資本主義経済は、高度経済成長と大衆社会の展開という、彼の考察が一見間違っていたかに見える状況を生み出した。それは、国際通貨基金と世界銀行が主導するブレトン・ウッズ体制の理想が曲がりなりにも機能していたからかも知れない。その理想とは「金儲けのみを志向する企業家や投資家の利益のためではなく、雇用・所得・社会事業など国民の利益のために、政府が通貨政策や税政策を通じて資本のコントロールを行う必要がある」というものである。しかし、現実にそこに存在したのは本当の意味での自由主義経済ではなく、資本至上主義というべきより悪化した姿で世界を席巻し、人間の本質を破壊する「悪魔の碾き臼」は別の形で破壊力をますます増大化させた。