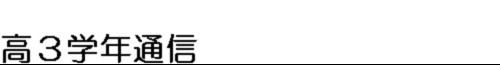ちょっと難しい経済の話
明日から3日間は、高校入試A日程とその選考会議等で生徒は休校です。今年はたくさんの受験生が本校を希望していますが、その背景には昨年の夏以降の世界的な不況も少なからず影響しているのではないかと考えられます。さて、今日は世界経済について考えてみるために、私がここ数ヶ月その著書を読んでいるカール・ポランニーに関する少し難しい経済の話を書いてみました。高一の生徒諸君は、休みの間に世界経済について少しでも考えてみましょう。
カール・ポランニー(KarlPolanyi,1886~1964)は、オーストリアのウィーンに生まれ、大学時代をハンガリーで過ごし、亡命先のルーマニアからイギリスからアメリカを経て、1964年にカナダで没した。彼は、経済学者であると共に経済人類学者として紹介されることも多い。ポランニーは、“異端の経済学者”と呼ばれる。それは、彼の研究テーマが約200年にわたる近代経済学が前提としてきた枠組みに真っ向から疑問を呈するものであったからである。
近代経済学の研究対象である市場経済の自己調整システムが全盛期を迎えたのは、19世紀のヨーロッパにおいてであった。しかし、それはマルクスが『資本論』で記録したように、過酷な労働を強いられる下層労働者と、膨大な植民地の犠牲に依拠したものであり、市場が人間=社会に従属させるという市場経済の矛盾の上に成り立っていた。ポランニーは、市場経済によって人間が蹂躙される状況を「悪魔の碾き臼」という例えで表現している。
そうした状況に対してポランニーは、マリノフスキーらの人類学研究の影響を受け、市場主義経済に新しい位置付けを与えた。それは、市場社会が登場する近代以前の社会では、経済は本来は「社会に埋め込まれていた」システムであり、市場経済のように経済が社会を従属させる「社会から突出した経済」は全くのフィクションに過ぎず、人類にとってはごく新しい、特殊なものであるということであった。さらに、市場経済では、本来商品化されることにそぐわない「労働」・「土地」・「お金」が擬制的商品として流通しており、このことが市場経済が社会を従属させている大きな原因であると考えた。「労働」とは「人間の生活の一部そのもの」であり、「土地」とは「人間が暮らすまさにその場所」であり、「お金」とは「本来価値を持たないもの」である、という至極当然の指摘であった。
19世紀には市場メカニズムに対する不可侵が自由主義思想の基本であった。しかし、市場の破壊的側面を、自由放任であるはずの市場は、社会の要請によって規制を要請され、世界の方向性はその間をめぐって揺れ動いていたのである。
20世紀初頭にいたると、「市場は自己調整によって維持される」という神話は崩壊し、社会主義国家ソ連の計画経済、世界大恐慌下でのアメリカのニューディール政策、ドイツやイタリア・日本というファシズム国家の出現という様々な状況が現れた。これらは、いずれも市場経済の矛盾に対する、「神の見えざる手」ではなく、「自由放任」を捨てた人間社会の側からの対応策であったといえよう。 (続く)
配布物:入試休みの間の自習用プリント(現文・古文)