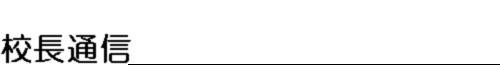二十四節気「大雪」に思う
きょうは二十四節気の21番目にあたる「大雪」です。「雪が激しく降り始める頃で、鰤などの冬の魚の漁が盛んになり、熊が冬眠に入り、南天の実が赤く色附く頃である」とされています。
さすがに、学校の周辺ではまだ雪が降る状態ではありませんが、寒さは一段と厳しくなってきていますし、南天の実は赤く色づいています。南天は、「難を転ずる」に通ずることから、縁起の良い木とされ鬼門や裏鬼門に植える風習があります。鰤(ブリ)については、江戸時代の本草学者である貝原益軒が「脂多き魚なり、脂の上を略する」と語ったところから、「アブラ」が「ブラ」へ、さらに転訛し「ブリ」となったとか、「『師走』(12月)に脂が乗って旨くなる魚だから」、「魚」偏に「師」と書くという説などもあるようです。またこの魚は、大きさによって呼び名が変わるところから出世魚といわれ、縁起の良い魚とされています。地方によって呼び方が変わりますが、関西地方ではツバス→ハマチ→メジロ→ブリと呼ばれています。
「南天」も「鰤」も縁起の良いものとされています。これは、寒い厳しい冬の季節に、少しでも明るく前向きに元気がでるように物事を捉えようとする、昔の人の知恵があらわれているような気がします。これから厳しい入学試験の季節を迎えます。小学生→中学生→高校生→大学生と「出世魚」のごとく呼び名が変わるよう、「学力」という「脂」をシッカリ乗せ、荒海を乗り越えて欲しいと思います。季節も「大雪」→「冬至」→「小寒」→「大寒」そして「立春」へと進んでいきます。