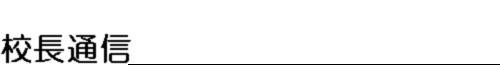「学び」のカギを握るものは
昨日のふたご座流星群を残念ながら私は見ることができませんでしたが、よく見えたといろんな人から聞きました。大阪の梅田に近いところでも良く見えたと、私の教え子からもメールが届きました。
さて、「学び」についてですが、カギを握るのは何かということです。そのことについて、先日PTAの講演会でお話していただいた内田樹先生が、中学二年生の国語教科書 (教育出版)に「学ぶ力」で以下のように書いておられます。
「『学ぶ(ことができる)力』に必要なのは、第一に、『自分は学ばなければならない』という己の無知についての痛切な自覚があること。第二に、『あ、この人が私の師だ』と直感できること。第三に、その『師』を教える気にさせるひろびろとした開放性。この三つの条件をひとことで言い表すと、『わたしは学びたいのです。先生、どうか教えてください』というセンテンスになります」。勿論、「師」は学校の先生だけを指しておられるのではありません。
「学び」は教育者と被教育者、指導するものと指導されるものとの間で成り立つものです。この関係の中で大きなカギを握るのが、被教育者、学ぼうとするものだということです。当然のことですが、教える側、指導者の役割を軽視しているのではありません。
このことは、自ら進んで学ぼうとする「学びを追求する生徒集団」の育成を掲げている私たちの考えと共通するものです。今一度、学びに対する自らの姿勢を問い直し、師から、「こんなことも教えたい」、「分かるまで教えてやろう」という気持ちを引き出す「師を見上げる真剣なまなざし」で授業に臨んでほしいと思っています。