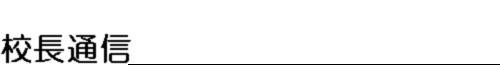「一陽来復」
昨日は二十四節気の22番目にあたる冬至でした。冬至は太陽の南中高度が一番低く、一年中で最も昼が短く、夜が最も長い日です。夏至と比べると札幌で6時間、東京で4時間以上も昼の長さが違います。
札幌と東京では経度にして約2度札幌が東にあります。ということは、太陽は東から昇りますので札幌の方が日の出は早いはずです。確かに夏至の頃はそうですが、冬至の頃は東京の方が早くなります。
その仕掛けには、地球が自転している軸、地軸が約23度ほど傾いているところにタネがあります。夏至の頃は北極側が太陽の方を向きますから、緯度が高いほど日の出が早くなり、日没が遅くなります。北極付近では日が沈まず白夜になります。冬至の頃はその逆になります。札幌は東京より緯度が約8度ほど北にありますので、夏至の頃は日の出が早く、冬至の頃は日の出が遅くなるわけです。
「冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力が甦ってくることから、陰が極まり再び陽にかえる日という意の『一陽来復(いちようらいふく)』といって、冬至を境に運が向いてくるとしています。つまり、みんなが上昇運に転じる日」(くらしの歳時記)、といわれています。昔から、冬至にはゆず湯に入って、「なんきん」を食べると良いといわれています。これも、「いろはにほへと」が「ん」で終わることから「ん」には「一陽来復」の願いが込められており、「なんきん」は「ん」が二回もつくので良い、とされているようです。
物事を静止して捉えると、冬至は太陽の力が一番弱い日です。しかし、変化の中で捉えると、これから強くなっていく日だといえます。変化の中で物事を捉え、プラス思考で考える素晴らしい伝統を大切にしていきたいと考えています。