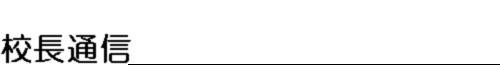学年末考査2日目
きょうは七十二候の第七項「蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく)」です。二十四節気では「啓蟄」にあたります。啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、大地が暖まり冬眠していた虫が、春の訪れを感じ、穴から出てくる頃とされています。害虫から守るために、松の幹に藁でできた菰を巻きつけたものをはずす「菰はずし」 を「啓蟄」の恒例行事にしているところも多いようです。春をよぶ東大寺二月堂の修二会(しゅにえ)、「お水取り」も始まっています。寒さもあと少し、もうすぐ暖かい春がやってきます。
虫や動物たちは陽気に誘われ動き出す時期ですが、私たちは、学年末考査の真っ只中です。毎朝、校庭で元気に遊んでいる生徒の姿が見られるのですが、さすがに試験が始まってからは見られません。放課後も同じです。代わりに、教室や図書室、学習スペースや交流スペースで一生懸命学習している姿が見られます。「動」に対する「静」です。「静中に動あり」とは、体は動かず静かにしているときでも、常に心は動かし周りの状況に気を配り、いつでも動けるようにしておくことをいいます。試験中は、まさにこれです。体の動きは最小限に、頭や心の動きは最大限に働かせるときです。試験が終われば、「動中に静あり」です。体は激しく動いているときでも、心は静かに周りの状況を的確に把握することが大切です。
学年末考査もそうですが、学生にとって進級試験、卒業試験や入学試験など重要な試験が春先に多いことから、試験は春を表す季語にもなっているそうです。