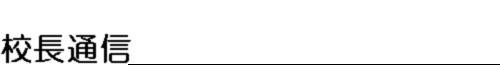国際人権規約
1966年の第21回国連総会において採択され、76年に発効した社会権規約と自由権規約(国際人権規約)を、日本は79年に批准しましたが、第13条2(b)及び(c)の規定を留保していました。この規定は、中等教育や高等教育は「無償教育の漸進的な導入により、すべての者に対して機会が与えられるものとすること」という内容です。30数年間この規定を留保していた日本政府は、昨年9月に撤回を表明しました。「この通告により,日本国は,平成24年9月11日から,これらの規定の適用に当たり,これらの規定にいう『特に,無償教育の漸進的な導入により』に拘束されることとなります」(外務省HPより)。今まで留保していたのは、約160の締約国のうち日本とマダガスカルだけで、国連は2001年に撤回を日本政府に勧告していたとのことです。
日本の大学の授業料は国際的にみて高額化しています。また、OECD加盟国の大半には公費による給付型奨学金があるのに対し、日本にはありません。なかには、大学の授業料が無料の国もあります。高校に目を向けますと、公立高校授業料無償化が実施されて3年、私立高校に通う生徒にも同等額の支援金が支給されるようになっていますが、公私間には納付金に大きな差があります。
公財政教育支出をみると、国内総生産(GDP)に占める割合が、OECD加盟国で比較可能な国で日本は最下位だそうです。公教育の一翼を担う私立学校と私立学校に通う生徒に対する補助が、「留保撤回」により「無償教育の漸進的な導入」が進むものと期待しています。