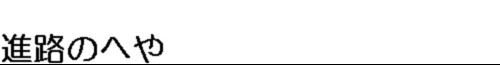one day college 感想文(22)-奈良女子大学-


理学部
-講義内容-
共生科学入門:生物共生の分子生物学
微生物と動植物の相利共生を中心に、共生の実例、共生を成立させる遺伝学的土台について概説した上で、共生と寄生の連続性や地球環境について概説します。まず、生物学における『共生』の定義づけ、成立要因にもとづく分類、多様で階層的な共生系の実例を紹介します。次に、マメ科植物と根粒菌が営む窒素固定共生について、共生成立に必要な遺伝子とその研究法を説明し、根粒菌と病原細菌の類似性についての最新の研究結果を照会します。また、地球上の物質循環における窒素固定共生の意義、そして環境問題との関連について考えます。
-生徒感想-
・去年、奈良女子大学のオープンキャンパスに行ったので、この講義を選びました。生物共生についてはよく聞いたりしますが、ここまで踏み込んだ話を聞いたのは初めてでした。互いに利益を与えながら生存し、一方が働なくなったら、逆に敵対関係になることがあるとは知りませんでした。遺伝子のゲノムを調べることで病気などの原因遺伝子を調べられる正遺伝学はおもしろいと思いました。本当にありがとうございました。(高2女子)
・生物はお互いにかかわりながら生きているのだなと思いました。虫、植物や海藻が、このよ
うな特徴をもっているのをきいて、私たちの身近でもたくさん共生植物を発見することができることを知りました。また、菌についても、私たちの体には何万個の菌がついていて、菌ときくと悪いイメージですが、それを除菌しすぎるとかえって良くないことも教えていただきました。生きているものは同じように見えても全く違う性質を持っているということがよくわかりました。(高2女子)
・この講義を聞いて、私は生物に対する興味や関心を改めて持つことができました。
私たちのための特別講義に加え、実際に大学でされている講義まで、いろいろな経験ができてとても有意義な時間を過ごすことができました。また、このような機会があれば、積極的に参加していくことで、実際に受験する大学の選択にも役立てていきたいと思います。(高2女子)
・共生には、相互的に利益を得られるものばかりだと思っていましたが、この講義を受けて、競合や拮抗などの相互利益的でないものがあると知り、とても驚きました。ずっと共生していても、一定の利益がなくなったら捕食対象になってしまったりするということも知り、生物界の厳しさも感じました。(高2女子)
・佐伯先生の授業を受けて「共生」についての理解が深まりました。また、具体的には、植物のリン酸が炭酸を取り込む仕組みを教えていただいたり、大学での勉強のあり方も知ることができてよい経験になりました。自分は、将来、マメ科の植物を研究したいと思っていますので、とても役立つ授業になったと思います。(高3男子)
・生物Ⅱの授業で最近習った「共生」を大学教授から教わったらどんな感じなのだろうと思って受けてみましたが、本当に有意義な100分になりました。私は以前サントリーの研究体験に参加したこともあるので、実験内容の用語も理解でき、とてもわくわくして楽しい時間でした。生物の資料集を見ながら受けたのですが、資料集にも載っていない詳しい共生の仕組み、種類をいろいろ説明していただき、とても勉強になりました。(高3女子)